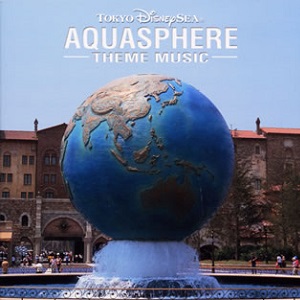私塾|音ノ雲 TOMITA Method × Case: NOJIRI トミタサウンドについて
シンセサイザーやオーケストラによる音楽表現、それらに伴う音響に対する考え方を冨田勲先生はどのように持たれていたのか。 |
||
冨田勲インタビュー記事 シンセサイザーと音響について |
||
MOOGシンセサイザーとの出会いはどのようなものだったのでしょうか?1970年大阪万博の東芝IHI館・全館の音楽担当をすることになったんだけれども、その時に「今までに聴いたことのない新しい音楽を」というオーダーだったんでね、 参考にするために、新しい楽器を使って演奏されたような音楽がないかとレコード店などを探していたときに、ワルターカルロスの「スイッチドオンバッハ」に出会ったんだよ。 当時、シンセサイザーなんていう言葉もない頃で、その「スイッチドオンバッハ」が、まったく新しい電子回路を演奏者が自分で結線して調整をして音を作ってから演奏されたと知って、 その楽器を探し始めたんだけど、誰も知らず。 パソコンやインターネットなんて影も形もない時代で、情報が皆無、実際に手に入れるまでは苦労したね。 |
||
具体的にどういったことがあったのでしょうか?情報がなかったので、探し出すのにもひと苦労。何と、たずねていったらアメリカのバッファローの郊外の野原のど真ん中のトサツ場跡のモルタルの平屋建てを改造したお粗末な工房でびっくりしたよ。 でも間違いなくMOOG博士がいてMOOGのいくつものモジュールを作っていたんだね。社員は総勢80人。とにかくそこから取り寄せたんだけれども、日本の空港の検問でひっかかったんだよ。 当時、誰もがMOOGシンセサイザーを見て「楽器」だとは思わなかったんだね(笑)。
|
||
冨田先生がMOOGシンセサイザーに興味を持った理由として、当時のオーケストラ生演奏による表現や音色に限界を感じておられたとのことですが、どのような点でそう感じられたのでしょうか?西洋の伝統ある音に対して興味がなくなった頃で、何か行き詰りを感じていたんだな、つまり、オーケストラでの表現は最高のレベルにまで到達してしまったと。 もはや、どのようにこねくり回しても同じような音にしかならないとモヤモヤとしていた。 バッハやその後のモーツァルトの時代からワーグナーまでの楽器というのは非常に進歩したと思うんだけれども、 それ以降の100年間は音色や楽器そのものに飛躍的な変化はないと感じていた。 そのときにMOOGシンセサイザーを使った「スイッチドオンバッハ」に出会って、「これだ!」と思ったわけ。 |
||
初めてMOOGシンセサイザーを操作し、音らしい音を出すまでに相当なご苦労されたと伺っております。試行錯誤の連続であったと思いますが、 そういった過程の中で「音色」に対する先生の考え方に変化はあったのでしょうか?もともと音色への拘りが深かった訳ですが、実際に原始的なところから音作りを始められて、何か発見はあったのでしょうか?つまり、ピアノの鍵盤を見て物理的に“有限”を感じていたのです。ところが、MOOGシンセサイザーの音色は人の声と同様、千差万別でドレミファソラシドという音階にとらわれることもなく、 行き詰まりはないと思った。 音程も音色もすごく“自由”になったと思ったね。
|
||
現在の作品では生楽器とシンセサイザーを音色として全て同列に扱っていると思いますが、それぞれの個性を活かすために何か、工夫なり配慮されていることなどはあるのでしょうか? また、改めてオーケストラを扱うようになり、今までの管弦楽法とは違ったアプローチがなされるようになったのでしょうか?僕もMOOGシンセサイザーを使っているうちに分かってきたんだけど、その区別はまったくないんだな。 シンセサイザーは人工的に試行をこらすので色々と工夫をしているのでは? とよく聞かれるんだけれども、それは生楽器であってもそれは同じで、例えばパイプオルガンは人工的に倍音を構築しているよね。 これは大変にメカニックなものだと思うよ。さっき、オーケストラの表現は同じような音にしかならないと言ってけれども、それは当時の僕がその一部分しか見ていなくて、そう思っていたわけで、 MOOGシンセサイザーを使った表現を探求することで、新たな生楽器の魅力を見出したよ。だから、手塚治虫氏の映画「新ジャングル大帝」はオーケストラのみで表現したよ。 ディズニー・シーの「アクアスフィア」の音楽もオーケストラ。「源氏物語幻想交響絵巻」はオーケストラもシンセサイザーも区別せず使ったんだ。 つまり、オーケストラを使うからオーケストラの音だけでなくてはならないという事はないと思うんだな。だから今のミュージシャンは大変恵まれていて、音源が多種多様で表現範囲がすごく広がったと思うね。 |
||
近年の、いわゆる「打ち込みサウンド」は生楽器を如何に再現するかに重きを置いておりますが、そのことについてはどう思われますか?それは割り切りだと思うね。予算に見合った方法をとるのは現実として必要だと思うね。打合せやデモの時に音源モジュールでの「打ち込み」は有効に使われるしね。 ただ、完全に生楽器やオーケストラを模倣するだけの表現に留まるのでは意味はないと思うね。 この行き方じゃ生楽器以上の表現は出来ないよ。
|
||
「惑星」のライナーノーツでは、ハープを例に挙げ、シンセサイザーでは実際の演奏上の制約を取り払った表現ができ、そもそも楽器の美しさはメカ的な制約であって、 本来の音色の美しさとは密着していないのでは?と書かれています。 現在のサンプラーでは高いクオリティーで音色そのものをライブラリ化し、自在に操ることができますが、そういった時代になった今はどのようにお考えでしょうか?いや、あるんだよね。制約があるから生まれる演奏表現が。 僕らが作曲の仕事をはじめた頃は、ベースと言えば弦バスしかなかったんだよ。弦バスは演奏に力が必要だし、単音のピチカートで4拍子の1拍3拍を弾くだけでも充実した低音が得られた。 ところがある日、突然エレキベースが出てきて、このエレキベースはあまり力を必要としないで、電気的に増幅するので、楽に低音が出せるんだけれども、弦バスの役割は任せられなかったね。 どうも音が薄っぺらというか、安っぽい。 これはいずれなくなる楽器だなぁと思っていた。 そうしたら、ランニング奏法という弦バスとはまったく違った奏法がロックミュージシャンの中から出てくるようになって、その新表現は今では当たり前に定着した。 つまり、楽になった分は、それなりの工夫をしないとダメなんだな。ある楽器を楽に音を出す為に、電気で増幅するという考えだけのことだと、それなりの音しかしないから聴衆に対して感情移入ができない。 ハープもクロマチックなど全て簡単に音が出るようになった場合、同じ問題があると思うね。楽器の構造なりデジタル機器の進化によって、演奏上の制約が少なくなり、何かが「便利」になったからと言っても、 それを使って表現することも伴って新しくならないと、まったく意味がないと思うね。和楽器なんかは非常にシンプルな構造で、西洋の楽器からすれば便利な機能が少ない、 だからといって表現力が劣るどころか文明に伴って改良された洋楽器以上の表現力があるよな。 |
||
「仏法僧に捧げるシンフォニー」を改めて見て感じたのですが、冨田先生がMOOGシンセサイザーを探求され、独自の表現を確立されてきたことは、再び生楽器やオーケストラを使われたときの“音場表現”へ影響しているように思いました。 幼少時代に経験された回音壁の面白い音の記憶から始まり、常に音響空間についてこだわりを持たれていたとは思いますが、 シンセサイザーの音色に音場が無かったことが、「源氏物語幻想交響絵巻」や 「アクアスフィア」のような集大成と呼べる作品につながっているのではと感じました。それはあるね。もともとオーケストラというのは、ほとんど楽器の配置は動かせないよな。しかし楽器としての存在感はある。 かたや、シンセサイザーで作られた音色は発振音がもとなので、奏者の息遣いなどはないし、それだけでは存在感がないどころか、まわりの音場も感じられない。 したがって、何らかの工夫をして存在の意味を持たせることが必要で、それで始めたのが「音の移動」だったんだね。 作品を聴いてもらうと分かると思うけれども、 これはアニメと同じで、シンセサイザー音の打ち込み演奏は、現実では考えられないような自由な音場表現ができるんだよ。 それで再びオーケストラの作曲に戻ったときに、 例えば「源氏物語幻想交響絵巻」はロンドンフィルの演奏のDVDオーディオのサラウンドのミックスダウンは僕自身がやったんだけれども、あれは「生霊」の声が後ろから聴こえたりして、 普通のクラシックのコンサートの実況録音ではあり得ないことをしたけれども、それが「邪道」といわれようがなんといわれようが、自分が作曲した曲なので根本がそういったイメージならばそれを貫くべきとおもったね。 平安朝時代の夢のような空間を作曲の延長として、5.1chサラウンド(コンサートホールでは7.1chサラウンド)の音場で表現した。
|
||
「仏法僧に捧げるシンフォニー」の放送後、一番多く聞かれたのが「あの壮大な発想はどこから出てくるのか?!」といった事でした。今日はその答えを垣間見られたような気がいたします。あの時は鳳来寺山の鏡岩や断崖絶壁や沢の響きをエフェクターとして利用したコンサートで、巨大な鏡岩の前でNUENDOにより僕のシンセの音の送り出しをしたんだな。 あそこは特等席だよ。雨が降ってきて急いでビニールで覆ったりして、まぁよくエラーもなく、あんなところでコンサートが出来たと思うよ。スタッフのみなさんに感謝だね。
|
||
はい。「仏法僧に捧げるシンフォニー」では、たくさんのことを学ばせて頂きました。ありがとうございます。 本日お話を伺って、生楽器からシンセサイザー、そしてその融合から生まれるトミタサウンドには、アーティストが「常識」に囚われることなく、 常に自由に、そして妥協無く探求する精神があるからこそ実現されるのだと感じました。音楽理論や楽式論、楽器や音響機器はあくまでアーティストの表現を支える為のものであって、 そこから発想が生まれるわけではないのを改めて感じます。素晴らしく発展した創作環境を活用し、新たな表現を生み出すのは今日のアーティストの役目であるとも思います。 本日はありがとうございました。 |
||
インタビュアー:野尻修平 |
||
関連記事 |
||
|
・トミタメソッドについて|TOMITA Method × Case: NOJIR |
||
関連リンク |
||
|
・冨田勲 - Wikipedia ・冨田勲 | 日本コロムビアオフィシャルサイト ・野尻修平 | 公式サイト ・私塾|音ノ雲 |
||
| TOMITA Methodを次世代に | ||
|
||